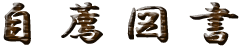99点
「神との対話」1~3巻「神との友情」上下巻「新しき啓示」「明日の神」「神へ帰る」
(ニール・ドナルド・ウォルシュ著 サンマーク出版)
予言はしないと言いながら、予言をしているのが、1点減点(「神との対話」試論参照)。
ただし、それ以外には実に驚くべき発想を分かりやすく説いている。
さすが、この世界の創造主とうなってしまうが、「神はこんな話し方をしない」という人もいて、そういう意味では軽い本である。
対話なのでどうしてもそうなってしまのであろう。
あるいは、著者のニール氏の人柄なのかもしれない。
重い語り口が好みの方には不満に感じられるかもしれない。
また著者というか、チャネラーというか、ニール氏がキリスト教圏の方なので、若干違和感をおぼえる記述が私にはある。
「愛」という言葉が頻繁に出てくることである。
しかし、その違和感を感じる私でも以下の愛の定義にはうなってしまう。
旧掲示板から何度なく引用した個所である。
こころを動かされた話しは数多くあるが、あえてこれを引用させていただく。
「純粋な真の愛をどう定義なさいますか?」
「誰にも被害を与えたり、傷つけたりしようとしないものだ。
誰かに被害を与えたり、傷つけたりする可能性を避けようとするものだ。」
「愛の表現によって誰かが傷つくかもしれないなんて、どうして予想できるでしょうか?」
「あらゆる場合を予想できるとは限らないだろう。
わからないときは、わからない。
それでも、あなたの動機は純粋だ。
あなたの意図は純粋だ。
あなたの愛は純粋だ。
だが、ほとんどの場合はわかりうるし、わかっているんだよ。
そういうときは、愛の表現が誰かを傷つける可能性があることははっきりしている。
そのときは、こうたずねたらいい。
いま、愛ならどうするか?
いまの好意の対象に対する愛だけでなく、ほかのすべてに対する愛もだよ。」
「でも、そんな「基本原則」を適用したら、現実に誰も愛せなくなります!ほかのひとが愛の名においてすることに自分は傷つくというひとは、必ずいますよ。」
「そう。あなたがたの種のあいだでは、癒そうとする手段ほど傷つけるものはない。」
「どうして、そうなるんでしょうか?」
「愛とは何かを理解していないからだ。」
「愛とは何なのですか?」
「愛とは、無条件、無際限で、何も必要としない。
無条件だから、表現するために何も求めない。
何の見返りも要求しない。
仕返しに出し惜しみすることもない。
無際限だから、他人に何の制約も与えない。
終わりがなく、いつまでも続く。
愛の経験には、境界も障壁もない。
何も必要としないから、自由に与えられるもの以外は何もとらない。
もってほしいと思われるもの以外は、何ももたない。
喜んで歓迎されるもの以外は何も与えない。
そして、愛は自由だ。
愛とは自由であるものだ。
自由こそ神のエッセンスであり、愛とは表現された神だから。」
(「神との友情」上巻186ページ)
99点「ハトホルの書」 (トム・ケニオン&ヴァージニア・エッセン著 ナチュラルスピリット刊)
このようなきれいな話し方をする存在に初めてふれた。
相手の自由を尊重する慈愛に満ちた言葉の使い方は驚嘆に値する。
常識から考えると受け容れがたい話しも出てくるが、その語り口ゆえに、信じがたいことも捨て去ることなく、理解できるまで待とうと思っている。
なお、「神との対話」とは異なった形で実践の方法を具体的に紹介している点からも読むに値する本であると思っている。
気のコントロール、感情のコントロール、音のバイブレーションの実践的な活用法が書かれてある。
本当は100点であるが、「神との対話」より上にはできないという意味での99点である。
冒頭からの引用。
「わたしたちは集合意識ハトホルです。
わたしたちは愛とともに、あなたがた地球の素晴らしい理想的な現実(リアリティ)の響きをたずさえてやって来ました。
もしみなさんに新しい世界をつくり出す用意があれば、一緒に知性と感性の旅に乗り出しましょう。
わたしたちはあなたがたの先輩であり、兄弟姉妹(きょうだい)にあたる存在で、この惑星で進化を遂げつつある人類をとても長いこと見守ってきました。
わたしたちは太古の昔から、あなたがたとともにあります。
わたしたちの足跡は、あなたがたの有史時代の記録に残っているよりさらに古い、いまや忘れ去られた時代までさかのぼることができます。
わたしたちは次元を超えたエネルギー的存在で、もともとは別の宇宙から、あなたがたの宇宙の入り口であるシリウスを経由してやって来ました。
そしてシリウスからあなたがたの太陽系へと入り、金星のエーテル界に落ち着くことになったのです。」
(17ページ)
シリウスとか金星のエーテル界とかいう話にはついていけない方もいらっしゃるであろう。
わたしは半々であるが、それはさておき、自分に役立つ話しだけを取り入れればいい。
これはすべての書、すべての体験に関していえることである。
そして、付言するならすべての自己表現いついてもいえることである。
<何がわたしの役に立つか>
ということは、この世界で受ける印象の際にも、この世界で表現する創造行為の際にも判断基準として役立つものである。
この意味で、この文章でわたしの役立つところは、
「もしみなさんに新しい世界をつくり出す用意があれば、一緒に知性と感性の旅に乗り出しましょう。」
という個所である。
誰もが共通意識(共通無意識と呼ぶのが正確か)として持っている、「日常の損得計算、身体感、物質感、人間関係感、……」などでなく、
<一緒に>
<知性と感性の旅>
に乗り出しましょう
と言っている。
そう、この世界は<知性と感性の旅>として見ることができるのである。
99点と点数をつけている以上、引用したい箇所はすべてといってもいいほどである。
ここでは、あえて、「アセンションのゴール」に関する彼らハトホルの見解をご紹介させていただく。
「わたしたちは次元を超えたエネルギー的存在で、もともとは別の宇宙から、あなたがたの宇宙の入り口であるシリウスを経由してやって来ました。」
という彼らの言の突拍子もない話しをおぎなう意味で、アセンション、すなわち次元上昇という怪しげな言葉に関する彼らの考えを引用させていただく。
考えはしごくまともであるということが、シリウスと経由してというSFまがいの話しももしかしたら本当かもしれないと思わせてくれるからである。
ここでアセンションに関するわたしたちの解釈と、その見解の傾向について述べておきたいと思います。
わたしたちにとっては、アセンションの有無に限って言えば、地球や人類がどう判断しようと、またいつどのようにそうしたことが起きようとあまり問題ではありません。
むしろ現時点で重要なのは、人類一人ひとりが自分のアセンションにおいて、自身のピラミッドの基点でどういう「選択」をするかです。
アセンションのプロセスには終わりはありません。
アセンションのゴールとは、ある特定の意識のオクターブに達することではなく、自分自身を愛にゆだね、そして人生に起こりくるさまざまな状況に対して最高次の可能性にゆだねることなのです。
そうすることが全体に貢献することになり、同時に個人が意識を高めることにもなると考えています。
ですからアセンションするかしないか、あるいは肉体上の死に向かうか否かは問題ではありません。
アセンションという現象をまるでマラソン競技のように見なし、最初にアセンションにゴールした人が「勝者」だと考える人もいるようですが、わたしたちはそういうふうには見ていません。
わたしたちの見解を明確にお伝えすることによって、その点をはっきりさせておきたいと思います。
わたしたちの考えは、何千年という歳月をかけてうまくいく方法を発展させてきた、その方法論にもとづいています。
その結果、わたしたちはもう一オクターブ上がることだけがアセンションの目的でないのを断言することができます。
その結果、わたしたちの念頭にあるアセンションのゴールとは、日常をできるかぎり豊かに精一杯生き、常に自分を愛と気づきという偉大な力にゆだねて生きることにほかなりません。
存分に生き、日々のどんな場においても最高次の可能性を生み出すように努めるなら、わたしたちの文化、種族、共同体、文明全体が高められます。
わたしたちが現在の次元にとどまるかどうかは問題ではありません。
なぜなら無限の大宇宙を生きるわたしたちは全員、いずれアセンションすることになるからです。
新しい千年紀にあたってのわたしたちのアドバイスは、時刻表やら現在の現象やらにあまり囚われないようにということです。
どんな現象も自然に収束するものです。
しかもそれらは大宇宙のなかで、人類の思考や干渉には影響されない部分に属するものなのです。
したがって、まずはあなたが手掛けられることから変えてゆくほうが、この場合はるかに有益であると思われます。
そして、あなたが手掛けられることというのは、あなたが世界にもたらす愛を増やすことなのです。
(159ページ)
いつも言うことであるが、普通がいい。
普通の日常にすべてが含まれている。
ただ、その普通のなかで、時代、地域、性差、財力、などなどにより、「含まれているすべて」が見えなくなってしまうことが問題なのである。
しょせんはすべてを見ることはかなわないことであるが、少なくとも汚れきった色眼鏡をはずしてみることはできる。
どのようにして色眼鏡をはずすかというと、それは、
<この世界のあらゆる自然、生き物、モノに親切に接する>
という、このことによってである。
次元上昇の鍵もここにある。
さらに言うなら、そしてこれこそがこれまでの人びとの生き方との大きな違いであるが、
<気づきをもった親切>
ということである。
昨日とは違う親切に気づき、実践するということである。
誰でもできる簡単なことである。
だが、もしかしたら、一生に一度か二度のことかもしれない。
そうとしたら、あまりに悲しいことである。
99点「逝きし世の面影」(渡辺京二著平凡社ライブラリー)
これも100点でもいい本である。
減点1点は、この江戸時代の世界を超えたいという願いからである。
わたし自身交友範囲が広いわけではないし、さほど売れている本でもないと思われるが、ふたりの友人が読んでいたというのが不思議といえば不思議である。
西洋──それは、われわれの今であるが──を取り入れたときに喪ってしまった日本の文明について書かれている。
今では想像もできなくなってしまった、社会、人間性が描かれている。
日本人であるなら、必読の書ともいえる本である。
以下は、冒頭にあるペリー提督の話しである。
こういう話しは100年たっても学校では教えてくれないであろう。
しかし、アーミッシュの学校、シュタイナーの学校であればもしかしたら教えてもらえるかもしれない。
「たとえばハリス(Townsend Harris 1804~78)が、1856(安政3)年9月4日、下田玉泉寺のアメリカ領事館に「この帝国におけるこれまでで最初の領事館」を掲げたその日の日記に、「厳粛なる反省──変化の前兆──疑いもなく新しい時代が始まる、あえて問う。
日本の真の幸福となるだろうか」としるしたのは、まさしく予見的な例といってよかろう。
このときハリスは、日本に上陸して二週間にしかなっていなかった。
彼はこの国の根本的な変貌を予感してはいたが、喪われるのが何なのか理解していたわけではない。
だがその二年後、下田に来泊したイギリスのエルギン使節団の一艦長に対して、彼は「日本人へのあたたかい、心からの讃辞」を洩らすとともに、「衣食住に関するかぎり完璧にみえるひとつの生存システムを、ヨーロッパ文明とその異質な信条が破壊し、ともかくも初めのうちはそれに替るものを提供しない場合、悲惨と革命の長い過程が間違いなく続くだろうことに、愛情にみちた当然の懸念を表明」せずにはおれなかったのである。」
(13ページ)
以下、ハリスの通訳のヒュースケンの話しの方が分かりやすいのだが、切りがなくなるので割愛して、そのハリスが「衣食住に関するかぎり完璧にみえるひとつの生存システム」と語った、その生存システムが「陽気な人びと、簡素さとゆたかさ、親和と礼節、雑多と充溢、労働と身体、自由と身分、裸体と性、女の位相、子どもの楽園、風景とコスモス、生類とコスモス、信仰と祭、心の垣根」と章別に語られている。
本当に全文を引用したしたいのであるが、そうもいかないので、とりあえずページをめくった二ヶ所「雑多と充溢」「心の垣根」より引用させていただく。
第5章雑多と充溢
「たとえば、時々小さな軽業師たちの一団を目にします。
年長の少年に率いられた子供たちで、馬車のあとからからだをよじってころびながら追いかけてくるのです。
こればかりは、日本人の関節はインドゴムでできていると確信しないかぎり、こわくて見てはおれないのです。
それから、行商人たちもいます。
古着屋だとか、羅宇(らお)屋とか。
羅宇屋は、わずか1厘で戸口に腰をおろし厳粛にキセルを掃除してくれます。
傘張り屋は、巨大な黄色のパラソルを陽にあてて乾かそうと道いっぱいにひろげます。
あるいはこちらでは、手品師が刀を呑みこんで、一群の子供たちをびっくりさせたり喜ばせたりしています。
また豆腐売りは、チーズのようなものの大きな厚い切れ切れを切り分け、お客の持ちかえり用にと、緑の葉に包んでいます。
私は路上の生活を観察するのが好きなのです。
その雑多さと充溢、その当惑させる率直さ、そして、曰く言いがたい控え目、帰宅するたびに心残りに思うのです」。
メアリにとってこの国は驚異だった。
彼女は日本へ向う船の中で、「世界でもっとも不思議な国について或る無内容な思い出だけを大事にする」ような旅行者にはなるまいと心に期していたのだが、長崎に上陸し瀬戸内を航行するうちに、「さかしらな心構えなどすっかりくつがえされて」しまった。
「ただただ、陽気な笑いの発作がこみあげてくるばかりでした。
涙を出さずにはおさまらない、喜ばしくたわいない笑いでした。
突然、人生が嬉しくいとおしいものに見え始めました」。
彼女は長崎の路上で見た菓子売りに、6ペンスを払って身代りになりたかった。
「その男のいでたちときたら、印象派風で、涼しいブルーの木綿地に、あまり目だたない巧みな筆致がほどこされ、後はただ褐色のからだとワラのサンダルだけでした」。
彼は「雪のような白木とデリケートな紙でつくられた妖精の厨子」を担いでいたが、それを遠くから眺めると「二本の茶色の茎の上に咲いた一束の蓮の花か」と思えるのだった。
(206ページ)
第14章心の垣根
「その安息と親和の世界には、狂者さえ参入を許されていた。
フォーチュンはディクソンら友人とともに鎌倉を訪ねたが、町中に入ると女が一人道路の真中に坐りこみ、着物を脱いで裸になって煙草を吸い始めた。
明らかに気が違っているのだった。
フォーチュンらが茶屋で休んでいると、彼女がまた現われて、つながれているフォーチュンらの馬に草や水を与え、両手を合わせて馬を拝んで何か祈りの言葉を呟いていた。
彼女は善良そうで、子どもたちもおそれている風はなかった。
フォーチュンたちはそれから大仏を見物し、茶屋へ帰って昼寝をしたが、フォーチュンが目ざめて隣室を見やると、さっきの狂女が、ぐっすりと寝こんでいる一行の一人の枕許に坐って、うちわで煽いでやっていた。
そしてときどき手を合わせて、祈りの言葉を呟くのだった。
彼女はお茶を四杯とひとつかみの米を持って来て、フォーチュン一行に供えていた。
「一行がみんな目をさまして彼女の動作を見つめているのに気づくと、彼女は静かに立ち上がって、われわれを一顧だにせず部屋を出て行った」狂女は茶屋に出入り自由で、彼女のすることを咎める者は誰もいなかったのだ。
当時の文明は「精神障害者」の人権を手厚く保護するような思想を考えつきはしなかった。
しかし、障害者は無害であるかぎり、当然そこにあるべきものとして受け容れられ、人びとと混りあって生きてゆくことができたのである。
(562ページ)
(類書)
生きるということは、自分自身の選択・自由を行使するということであるが、そのような第一原因以外に、ある力に手繰り寄せられるような形で生きざるをえないこともある。
そして、そのようにして手にする本もある。
上記の「逝きし世の面影」もそうであったし、以下のラフカディオ・ハーンの著書もそうである。
90点「新編・日本の面影」 (ラフカディオ・ハーン著池田雅之訳角川ソフィア文庫)
実に秀逸な視点の話しを二ヶ所引用させていただく。
(ラフカディオ・ハーン著池田雅之訳「新編・日本の面影」ページ角川ソフィア文庫)
認めにくいことかもしれないが、もしかしたら読者が心底ほしいものは、店においてある商品ではなく、その店であり、店員であり、のれんも住人もひっくるめた、店々の並ぶとおりである。
さらには、町全体であり、入り江であり、それを取り巻く山々であり、雲ひとつない空にそびえる富士山の美しい白い頂ではなかろうか。
実のところ、魅惑的な樹木、光り輝く大気、すべての都市、町、寺、そして、世界でもっとも愛らしい四千万人の国民も一緒に、日本全体をまるごと買ってしまいたいのだ。
(20ページ)
020~芸術家
ここでかつて日本の大火のことを耳にした、ある実利的なアメリカ人の発した言葉を思い出した。
「ああ、日本人なら火事にあっても大丈夫だ。
日本の家は、とても安く建てられているから」。
庶民のもろい木造家屋は、たしかに費用はかからないし、すぐに建て替えはきくだろう。
しかし、もとの家にあった美しさは、もう取り戻すことはできない。
それを考えると、どんな火事であろうと芸術にとっては悲劇である。
さまざまなものが無限に手作りされてきた国だからこそ、それはなおさらのことだ。
機械はまだ、(諸外国の需要に応じて、低俗な市場に合わせた悪趣味なものを作ることを除いては)、廉価商品に見られる画一化と、実用のみを求めた醜さを生み出すまでには至っていない。
工匠や職人が作ったものは、他人の作品とは違っており、たとえそれが、自分の作品であっても、ひとつひとつ異なっている。
だから、何か美しいものが火事で焼けるたびに、たったひとつしかない意匠も消えてゆくことになるのだ。
幸いにも、この火災の多い国では、芸術への衝動自体が、代々の芸術家を越えて生き残る生命力を秘めており、それゆえ、かつての名匠の労作を灰燼と帰し、ぶざまに解かしてしまう炎にも、敢然と立ち向かってきた。
意匠というのは、たとえそれを表現した作品が消滅したとしても、おそらく一世紀ほどの時の流れを経て、再び違う創作の形で甦(よみがえ)るものである。
実際には、姿形に変更はあるだろうが、過去の思想の流れを汲(く)んだ作品であることは、容易に判別できるであろう。
もともと芸術家とは、みな霊的なものに導かれた職人なのだ。
本人が何年もの歳月を模索し、犠牲にすることによって、高度な表現を会得するのではない。
犠牲的な過去は、すでに本人の中に潜んでいるものであり、技芸はすでに受け継がれている。
その指が、死者の導きにより、飛ぶ鳥、山々の霞(かすみ)、朝や夕暮れの色、小枝や春に咲き乱れる花々を描いてゆくのだ。
何世代もの有能な職人たちから受け継がれた熟練が、今ここにひとりの芸術家の傑作の中へと甦るのである。
最初のうち意識していた努力は、数世紀後には無意識となり、現存の作家にはほとんど反射的といえるような、直観の芸術となるのである。
それゆえに、もともと何銭という安値で売られていた北斎や広重の色版画には、日本の町全体を買い取る以上に高いといわれる多くの西洋画よりも、それ自体ずっと本物の芸術味が詰まっているといえる。
(20ページ)
文字による具体的な描写というのはあまり好まないが、ハーンの文章は訳者の功もあると思うが、引き込まれてしまう。
以下、長文の引用になるが、割愛のしようがない。
静かで古びた、小さな宿の前で、俥を止める。
かなり年を召した宿の亭主が、出迎えに出てきてくれた。
その一方で、静かでおとなしい村人たちが──そのほとんどが、子供や女たちだったが──外国人を一目見ようと、人力車のまわりに集まってきた。
外国人の姿に目を見張ったり、興味深そうにはにかんだ笑みを浮かべながら、私の洋服に触ったりするのである。
私は、老齢の宿の主人の顔を一目見て、ここにお世話になろうと決めた。
明日まで滞在することにする。
車夫はあまりに疲れていて、今晩はもうこれ以上走れそうにないからだ。
そのこぢんまりとした宿は、外から見ると、風雨にさらされて古びたような感があったが、中は快適であった。
磨きこまれた階段や縁台には、汚れひとつなく、まるで鏡面のように女中の素足が映って見える。
明るい部屋は畳を敷いたばかりのようで、真新しく、甘い香りが漂っている。
部屋の床柱は、黒い立派な木材でできていて、そこに彫られた花や葉の模様には、私も目を見張った。
掛け物には、福の神の布袋(ほてい)様が、紫に煙る神秘的な夕暮れの中を、小舟に身を委(ゆだ)ねて霞(かす)む川を下っていく牧歌的な風景が描かれている。
この村落は、美術の中心地から遠く離れているというのに、この宿の中には、日本人の造型に対するすぐれた美的感覚を表してないものは、何ひとつとしてない。
花の金蒔絵(まきえ)が施された時代ものの目を見張るような菓子器。
飛び跳ねるエビが、一匹小さく金であしらわれた透かしの陶器の盃(さかずき)。
巻き上がった蓮の葉の形をした、青銅製の茶托(ちゃたく)。
さらに、竜と雲の模様が施された鉄瓶や、取っ手に仏陀の獅子の頭がついた真鍮(しんちゅう)の火鉢までもが、私の目を楽しませてくれ、空想をも刺激してくれるのである。
実際に、今日の日本のどこかで、まったく面白味のない陶器や金属製品など、どこにでもあるような醜いものを目にしたなら、その嫌悪感を催させるものは、まず外国の影響を受けて作られたと思って間違いない。
ところが、私は今、古い日本の村にいるのだ。
ここで、西洋人である私の目に触れるものは、何もかもこれまで西洋人が見たことのないものばかりなのである。
ハートのような形をした丸窓から、庭が望める。
すばらしいその小庭には、小さな池におもちゃのような橋が架かり、凡才のような小さな植えこみがある。
まるで、湯飲み茶碗(ぢゃわん)に描かれているような風景である。
もちろん庭には、格好の良い石や、寺の境内にあるような優雅な石灯籠(いしどうろう)も、置かれている。
その向こうに、暖かい夕暮れの中に灯(とも)っている、盆灯篭の灯影(ほかげ)も見える。
それは、愛しい死者の霊が帰ってくるのを、家に迎え入れるために、各家庭の軒先に吊(つ)るされる灯篭の明かりである。
この古い村では、まだ暦は旧暦に従っていて、それによると、今宵(こよい)は旧盆の初日にあたるのである。
これまで立ち寄った小さ田舎の村々と変わらず、ここの村の人たちも、私にじつに親切にしてくれた。
これほどの親切や好意は想像もできないし、言葉にもできないほどである。
それは、ほかの国ではまず味わえないだろうし、日本国内でも、奥地でしか味わえないものである。
彼らの素朴な礼儀正しさは、けっしてわざとらしいものではない。
彼らの善意は、まったく意識したものではない。
そのどちらも、心から素直にあふれ出てきたものなのである。
彼らと二時間も一緒に過ごしているうちに、彼らから受けた歓待にとても応(こた)えきれないと私は思うようになり、ふと脳裏に邪(よこしま)な願望がよぎった。
この愛しい村人たちが、私の予想を裏切るようなけしからんことを、私が驚いてしまうような悪事を、あるいは何かひどく薄情なことでも、私にしでかしてくれないだろうか。
もし、彼らが私にそうしてくれたなら、彼らと別れても、私は別に嘆かなくても済むからである。
このままでは、私はここを立ち去った後、すぐに名残惜しくなってしまうだろう──。
宿の老主人は、私を風呂場へ案内すると、まるで私が子供だといわんばかりに、私の背中を流しましょうと言ってきかない。
女将(おかみ)さんの方は、ご飯に卵、野菜にデザートといったご馳走(ちそう)を用意してくれた。
そして、私が満足できたかどうか気の毒なほど気遣うのである。
私は夕飯を二人前はゆうに平らげたというのに、女将さんは、たいしたおもてなしができなくて申し訳ありません、と何度も何度も詫(わ)びるのであった。
「今日はお盆の十三日なので、魚が出せないのです。
今月は十三日、十四、十五日と、誰も魚を口にしてはいけないことになっています。
十六日の朝になれば、漁師は漁に出かけるので、両親ともに健在であれば、その日は魚を食べることができます。
でも、片親でも亡くしていたら、十六日も、魚を食べることはできません」
人の好(よ)い女将さんからこうした説明を受けているうちに、私は表のどこか遠くの方から、耳慣れない音が聞こえてくることに気づいた。
(56ページ)
実は、ここから盆踊りの記述になるが、現代の盆踊りとは似て似つかぬ幻想的な光景が描き出される。
ぜひお読みいただきたい。
なお、ハーンはアイルランド人である。
80点 「エリック・ホッファー自伝」 (エリック・ホッファー著中本義彦訳作品社)
正規の学校教育を一切受けずに、49歳で処女作「大衆運動」を発表し、大学で政治学を講じたが、終生港湾労働者として働き、「沖仲仕の哲学者」として知られているエリック・ホッファーの自伝である。
普通でない人生は始まりからして普通でない。
「不思議なことに、幼いころの記憶は曖昧である。
七歳のとき、私は視力を失った。
五歳のとき、母が私を抱いたまま階段から落ちている。
それがもとで母は体をこわして二年後に亡くなり、その年私は失明した。
しばらくの間は記憶もなくした。
妻に先立たれ盲目の息子を抱えた父が、私のことを「白痴の子ども」と呼んでいるのを聞いたことがある。
記憶のなかの母は小さくて、いつも何かにおびえていた。
それでも大きくなった五歳の息子を抱きかかえていたぐらいだから、たぶん私のことを愛していてくれたに違いない。
いまでも時折、母の指が背中に触れている気がして、夜中にふと目を覚ます。
鮮明に思い出せることが、二つある。
幼いころ私がぐずると、母とマーサはよく、備えつけの本棚のそばにあったテーブルに私をすわらせた。
父は独習の家具職人だったが、本棚には哲学をはじめ、数学、植物学、化学から音楽、旅行にいたるまで百冊近い英語とドイツ語の蔵書があった。
私は本棚にあった本を大きさや厚さ、色で分類して遊ぶことに夢中になる。
さらには英語とドイツ語の本を分けられるようになった。
そしていつのまにか内容によって本を分類できるようになったのだ。
五歳になる前には英語とドイツ語が読めたということだろう。
この分類への情熱がもたらした重要なことがもう一つある。
後年、思索し、ものを書き始めたとき、気がついてみると私は相変わらず分類をしていたということだ。
事実と印象を区別し、照らし合わせていたのである。
もう一つの思い出は、九歳のときに父と一緒にタクシーに乗って、ニューヨークのコンサート・ホールにベートーヴェンの交響曲第九番を聴きに行ったことだ。
その日、父はいつものように振る舞っていたが、めずらしく興奮しているのがわかった。
クラシック音楽を愛していた父は、演奏予定のベートーヴェンの曲にも造詣が深く、「ベートーヴェンが聴力を失ってから作曲した第九は、神聖なメロディーが織りなすタペストリーだ」と言いながら、しばしばその曲を口ずさんでいた。
とくに第三楽章は壮大だとも語っていた。
コンサートがどれくらい続いたのかおぼえていないが、第九の第三楽章が演奏されているときのことだ。
父が私の腕をぎゅっとつかみ、私は翼が生えたように気分が昂揚した。
後に視力が戻って世の中に出てから、寂しいときや落ち込んだときには、気がつくといつも第九の第三楽章を口ずさんでいた。
1941年に十年間の放浪生活の末、やっとサンフランシスコに居を定めたとき、最初にしたことはプレーヤーと第九のレコードを買うことだった。
しかし、どのレコードを聴いても、第三楽章は私がおぼえている演奏とは異なるものだった。
どれも演奏が速すぎて無造作に聴こえ、訴えかけてくるような哀しみが伝わってこなかったのだ。
十五歳のとき、私は視力を回復する。
けれども、なぜ突然失明し再び目が見えるようになったのか、とくに思いわずらうこともなかった。
というのも、マーサがよく冗談で、ホッファー家が続いていること自体、奇跡だと言っていたからである。
実際、私の家系はみな短命で、五十歳以上生きた者は一人もいない。
「将来のことなんか心配することなんかないのよ、エリック。
お前の寿命は四十歳までなんだから」──マーサのこの言葉は私の心の奥深くに刻み込まれ、そのおかげで季節労働者をしていたときも、あれこれ先々のことを思い悩まずにすんだ。
私は旅人のように生きることができたのである。」
(7ページ)
いかなる環境いかなる状況にあっても、それを生かすことも殺すこともできる。
しかし生かすためには、やはり一度は死んでみなければならないのかもしれない。
以下は、28歳のときの話しである。
「私は腕に抱えていたビンを持ち直し、「この通りに終わりがなければ……疲れもせず、悩みも不満もなく、このままずっと歩いて行ければいいのに」と強く思った。
緑の草原と果樹園を抜け、青い海に出る道を思い浮かべた。
足と腕をふり、ナップザックを揺らしながら歩くことほど楽しいことはないだろう。
どこまでも続く道としての人生という不意に浮かんだ考えが、自殺への抵抗の最初の暗示だったことに、そのときは気づいていなかった。
もう道は泥道になっていた。
処刑台のような油井やぐらが、急に目の前に現れた。
道の左側の野原には、高く伸びたユーカリの木がぽつんと立っている。
足場の悪いでこぼこの地面をよろめきながら、そこまでたどり着いた。
ビンを包みから取り出している間、熱にうなされたように思いがかけめぐる。
私はビンのふたを外し、口いっぱいに一気にシュウ酸を流し込んだ。
口中に百万本の針が突き刺したようだった。
激情に打ち震えながら、シュウ酸を吐き出した。
つばを吐き、咳をし、唇をぬぐいながら、暗闇にビンを投げ捨てた。
つばを吐き、咳をし続けながら、急いで道へ戻った。
泥道を走り抜け、セメント道に入った。
舗道に響く足音は拍手のようだ。
興奮して、独り言を言いながら、群集にたどり着くまで走り続けた。
ランプも、点滅する信号も、鳴り響くベルも、路面電車も、自動車も、人間が作ったすべてが自分の骨身の一部のように思える。
ひりひり痛むほどの空きっ腹を抱えて、カフェテリアに向かった。
食事をとると、一本の道──どこへ行くのか何をもたらすのかもわからない、曲がりくねった終わりのない道としての人生という考えが、再び頭に浮かんできた。
これこそ、いままで思いもよらなかった、都市労働者の死んだような日常生活に代わるものだ。
町から町へと続く曲がりくねった道に出なければならない。
それぞれの町には特徴があり目新しく、それぞれが最高の町だと主張して、チャンスを与えてくれるだろう。
私は、それをすべて利用し、決して後悔しないだろう。
私は自殺しなかった。
だがその日曜日、労働者は死に、放浪者が誕生したのである。」
(45ページ)
生きるも死ぬも紙一重、放浪者であろうと労働者であろうとそのような選択の連続であるが、放浪者であればひとつひとつの選択の重みは違ってくる。
彼は常に放浪者としての自由の選択をしつづける。
その最たるものは、以下の話しである。
「それまで独りで勉強を続けてきたが。
どういうわけか動物学と植物学には手をつけたことがなかった。
化学、物理、鉱物学、数学、地理については大学の教科書をマスターしていたが、身のまわりにいる動物や植物はあまりに複雑かつ神秘的であり、厳密な科学研究の対象にはなりえないと思っていた。
しかし、ちょっとしたきっかけで、私は植物学にもめり込んでいったのである。
私は毎年、ナイルスの苗木畑で数週間過ごしていた。
成長の香りがあふれる温室の湿った空気が好きだった。
その年、ずっとトマトの苗木をボール紙の鉢に移し替えていたが、あまりに退屈な仕事で続けられそうもなかった。
ある日の午後、苗木の細根から土をほぐしていると、ある疑問が浮かんできた。
なぜ苗の根は下に向かって伸び、茎は上に向かって伸びるのか!それはなぜ私が息をしたり、寝たりするのかというのと同じくらい、面白いほど素朴な疑問だった。
誰かが同じ疑問を感じ答えを出しているに違いなかったし、植物学の教科書を調べさえすれば答えはわかるはずだ。
しかし、私はいますぐその答えが知りたかった。
すぐさま事務所に行って給料をもらい。
貨物列車に飛び乗り、サンノゼの近くまで行った。
そこの図書館には植物学の教科書が何冊かあり、そのなかで一番厚いのを手にとったが、それはドイツ語から翻訳されたシュトラスブルガーの本だった。
私は部屋と皿洗いの仕事を確保して、その本を読み始めた。
ところが、ほとんど読み進められない。
ラテン語やギリシャ語が頻繁に出てきて、辞書も役に立たない。
私があきらめかけていたそのとき、信じられないような偶然が窮地を救ってくれた。
ある日、図書館の近くにある古本屋の廉価箱を見ていて、たまたま安っぽい紙に包まれた薄い本を手にした。
それはドイツ語の植物用語辞典だった。
編者はベルリンの農業大学で植物学を講じているミューエ教授。
申し分のない、期待通りの代物で、用語の意味と語源の解説に加え、主要な植物学の小伝と有名な植物研究所の紹介まである。
しだいに私はこの小事典に愛着をいだくようになり、どんな質問にも答えてくれる不思議な賢人のように感じて愛用した。
むさぼるようにくり返し読んだ後も、ずっとナップザックの中に入れて持ち歩いたのである。
何年も後になって手放したが、その別れもまた劇的なものであった。
貨物列車の屋根の上でのことだ。
植物学とはまったく関係のない思想の難問を考えつづけていたが、暗礁に乗り上げていた。
その問題を解くにはより深く考え抜かなければならない。
と、そのとき私の手が無意識にナップザックに伸び、ミューエの“賢人”を呼び出そうとしているではないか。
どんな問題であれ、つねに答えを知っている人間がそばにいたら、自分自身で深く考えることをやめてしまうだろう。
そうすれば、私はもはや本来の思索者ではない。
不愉快な発見だった。
私はそうなることを拒み、ミューエの“賢人”を風の中に放り投げたのだ。」
(83ページ)
だが、どのような人の人生もそうであるが、常に最善の選択ができるわけではない。
放浪中に相思相愛となった大学院生ヘレンとの別れの話しである。
「彼女たちにはある計画があったのである。
ある晩、フレッドが人生の目的について私を諭した。
人間は目的をもっていなければならないし、自分の非凡な能力を無駄にするのは罪だ、と。
彼女はヘレンから最近の物理学の動向について聞かされていたのだ。
そして、私の理論化する才能を生かせば、奇跡的なことが成し遂げられるはずだし、物理学の誰よりもすごいことができる。
並外れた数学の力があれば、アインシュタインのようにもなれるかもしれない、と彼女は信じ込んでいた。
ばかげた話だった。
二人の女性が、私を驚異の人物に仕立てようと決意している。
まったく常軌を逸していた。
私は心からヘレンを愛していたが、彼女たちの期待に応えるために、四十歳まで残されたわずかな人生を費やすのは、あまりに惨めだろう。
おそらく物理学部の人たちは、すぐに私が偽者だと気づき始めるだろう。
どうして自分に並外れた才能があるなどと信じられよう。
もしこのまま彼女たちと暮らせば、一時の平和も見出せないだろうと思った。
私は一刻も早く行動を起こして、放浪生活に戻らなければならなくなった。
こうして収穫期が近づいたある日、私は何も告げずに、バークレーを離れた。
ヘレンたちとの別れから立ち直るには、何年もかかった。
いや、実際には、決して完全に立ち直ることはなかった。
心が引き裂かれるように感じただけでなく、体調のバランスも崩した。
体にはできものができ、目がかすむようになり、眼鏡をかけなければならなくなった。
その年の冬は彼女たちのいるバークレーを避け、サクラメントで過ごした。
私は人生で初めて寂しさを知った。
喪失感と絶望感にさいなまれた人間は、自分がどこから来たのか、そしてどこへ向っているのか、わからなくなるものである。
歴史を失うのだ。
この時期について、私は曖昧な記憶しか持ち合わせていない。」
(111ページ)
だが、どれだけ間違えてもそれは人生であり、道であるということである。
そして、誰にもそれは間違えであったとは言えないものである。
生きるとは、そういうことだ。
ずいぶん長々と引用したが、ヘレンの話しの次章に放浪先で一緒に綿摘みの仕事をしたアンスレーの話しが出てくる。
ヘレンの話しの後編とでもいうべき、ヘレンの後日談でもある。
これはぜひ本をお買い求めの上、お読みいただきたい。